試評 2004.09.03 by 土屋誠一
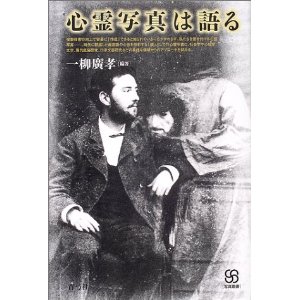
日本語で書かれた研究書としては、心霊写真について初めて纏まった議論を読むことのできる、一柳廣孝編著『心霊写真は語る』(青弓社)が先頃刊行された。写真というメディアを通じたイメージのインデキシカルな性質を考えるにあたっても、心霊写真とはすぐれてポレミカルなテーマであると言えよう。ベンヤミンがアジェの写真に「犯行現場」の痕跡を見出したことを代表例として、常に写真に現れる「心霊的」な表象のあり方が問題になってきたように思われる。
私事にわたって恐縮だが、幼い当時、心霊写真が本当に怖かった。私が小学校低学年だった頃、心霊ブームはまだ過ぎ去っておらず、その手のオカルトものに興味津々の同級生やらが、得意気に分厚い文庫サイズの写真集を見せびらかすのであった。あまりの恐怖感ゆえ、瞥見するやいなや、そのイメージが脳裏に焼き付いてしまう私には、それらを凝視するほどの勇気や忍耐の持ち合わせは、当然ながらまったくなかった。振り返ってみると、幼い頃の私が(いや、正直に告白すれば、現在の私にもその多くが当てはまるが)忌避していたのは、心霊写真やその他オカルティズム全般のみならず、「死」を強く想起させるイメージのほとんど全てだった。
しかし、この『心霊写真は語る』に収められた新旧の心霊写真からは、奇妙なほどに、ほとんど恐怖の感情を得ることがなかった。試みに、1970年代以降の、心霊写真ブームの嚆矢と言われる、中岡俊哉編著『恐怖の心霊写真集』(二見書房、1974)[註1]を見ても、ほとんどがゲシュタルト心理学的な形態把握とキャプションの操作によるものであり、あからさまに像が見えているものでも、二重焼付や撮影ミスによることが明白なものばかりであった。これにはいささか拍子抜けしてしまった。心霊写真が心霊写真として機能し、認定されるためには、ある時代相をプレテクストにする必要があるということであろう。であるならば、恐怖の対象として心霊写真を語るならば、それは、都市民俗学[註2]的視点において解決すべき問題である。その場合、恐怖をめぐる信仰や噂話を成立させる媒体として、写真が選択されているのであり、その媒体はあくまで可変項に過ぎない。ここでは、『心霊写真は語る』所載の論考[註3]から離れてしまうかもしれないが、写真というメディア的特質に即して、心霊写真を考えてみたい。超越的な存在の現れに対しては、原理的なレヴェルにおいて対処を試みるという選択もまた、誤ってはいないと思われる。
ニュートラルな鑑賞条件を要請する、抽象的な空間に展開する蜃気楼のような「写真作品=芸術写真」とは違い、心霊写真は例えばプリントそのものが宗教的儀礼によって「祓い」を受けるように、何か無気味なものが祟る「もの」として物象化され、畏怖すべきものとして客体化される。客体化された写真は、それ自体交換不可能なものである。ある個人にとって「祟っている」と見なされる一葉の写真は、「その」写真において祟っているのであり、それはなにか他の写真においてではあり得ない。心霊写真において重要なことは、「写真作品=芸術写真」の体験がしばしばイメージの読解作業に従事することに陥りがちであるのに対して、一度見た無気味なイメージは繰り返しの注視を必要とせず、イメージから瞬間的に把握した体験の強度のみにおいてその経験が反復される。作品化された写真は、見ることとそこからその都度受ける体験が不可分であるのに対して、心霊写真において一度得た経験は、瞬時にイメージから切断され、経験の強度のみが自立し続ける。さらに言えば、経験の強度さえ保証され得るならば、内在的にイメージを産出すれば外部の参照項としてのイメージは必ずしも所与ではないということでもあると言えるかもしれない。
無気味なものは、親密さの姿をまとって再帰する。上記のような経験は、E. T. A. ホフマンの「砂男」から、フロイトが読み取った概念のそれ[註4]と近似する経験であるだろう。「無気味なもの」の経験は、必ずしもその客体が現前することを所与とするわけではない。にもかかわらず、それは常に主体に対する外部として「ある」。親密であるがゆえに忌避され、見えていないがゆえに見えるという心霊写真の性質は、「無気味なもの」のパラドキシカルな条件に合致する。フロイトが述べる親密さとは、同一なものの反復を指す。反復による同一なものの二重化(ドッペルゲンガー)は、その二重化ゆえに同一性を保証する主体=自我を欠き、まさしく亡霊(心霊)のような存在になる。フロイトはオットー・ランクの言葉を引きながら、自我の消滅を保証するのは、死を否定すること=不死であると指摘する。「無気味なもの」を経験する強度は、同一なものの反復、フロイトに即して言うならば、反復強迫によって支えられる。この「無気味なもの」=心霊写真の経験における反復強迫は、死の欲動によって駆動させられるわけであり、それは自己の死の欲動を二重化された同一性に外化させることによって、代補的にそれを補填するということにほかならない。
しかしながら、このことは心霊写真に特有の事態であって、写真一般には適応されえないというわけではない。アジェの写真からベンヤミンが読み取るアウラの問題[註5]は、このことに関わっている。アウラの現前は、対象の同一性を前提とする。ベンヤミンがアウラの崩壊、反復性・複製技術に託したのは、近代以前の同一性の信仰が不確かなものであることを指し示すためにあった。しかしこれは、単にAのものがBに変化したというような、歴史的な切断と交替を示しているわけではない。ベンヤミンは対象を像(Bild)と模像(Abbild)に弁別し、後者を構成する知覚様式は単一なる像から同種のものを生産すると述べられるように、両者は知覚におけるパラダイムの交替ではなく、互いを含みこむかたちに入り組んでいるのである。だがなぜ、そのことが犯行現場の痕跡を想起させることになりえるのか。
ベンヤミンの議論は、一見すると複製技術を介したアウラの消滅によって、それまでのアウラをまとった客体から疎外されるような主客の距離的隔たりを克服し、反復性が生産する客体の遍在性において一挙に隔たりを縮減するといったような、ユートピックな社会モデルを想定しているように見える。しかし、模像=複製技術は、単にアウラの喪失を担うのみにとどまらず、逆説的にアウラを回復する、隔たりを回復する契機を内在している。むろんその契機は、犯行の痕跡や、心霊のような、インデキシカルなレヴェルの符号を求める限りにおいては解決不可能なものを認識してしまう地平、いわゆる「視覚的無意識」の地平において、発現する。言い換えれば、主客の唯物論的な関係から、超越論的な契機を認識するその一点において、アウラの所在は不確定なものへと転ずるのである。ここにおいて、インデキシカルな符号の欠如は不可欠であろう。この参照関係を欠いた認識の強度は、「無気味なもの」の発現がそうであったように、実際に参照しうる保証を欠いたままに、その強度のみが確実に把握されるという点において、アウラを回復する。欠如において存在の亡霊的な立ち現れを見て「しまう」ということは、一般に信じられている写真の明証性が何ら確かなものではないという事実の下に、その価値を失墜させることにつながる。
ベンヤミンのアジェに関する議論に対して、ジョアン・コプチェクは的確な表現を行っている。「アジェのこうした写真に、犯罪の証拠は一切映っていないことにご注目されたい。それが空っぽであることが証拠なのである。この欠如は、犯罪があったのではないかという疑念をいささかも弱めない。むしろ欠如こそ疑念の源であり、別な言い方をすると、われわれの心を掴むのはサスペンス(suspense)の証拠ではなく、証拠の宙づり(suspense)なのだ。」[註6]つまり、写真とは、不確定であり、決定不可能であり、解決不可能な関係性を産出する。それでは写真とは一体何であり、どこに所在し、どのように名指すことができるのであろうか。それは、主客の不分明な境界線、両者の位相を攪乱する折り目であり、あらゆる決定を留保(suspend)する、まさしく霊媒=媒体(medium)であるとしか言いようがない。
しかし、なぜ写真において、そのような事態が起こりえるのであろうか。一般的に信仰されているイメージの生成において、常に意志的な主体の選択が介在するが、写真は、決定する主体を要請しないという本質的な点において、徹底的に受容器でしかありえない。反復的にイメージを生成する受容器である写真の認識は、私の認識との距離を限りなく近似させる。その意味においては、視覚的無意識は私という主体に関しての議論ではなく、むしろ写真の認識と私の認識の二重化における無意識の立ち現れであるといいえるかもしれない。つまり、視覚的無意識は、より正確に言えば「写真的無意識」にほかならない。写真化された私の自我は、反復によって二重化=複数化のプロセスを経て、ただひたすら欠如の経験に畏怖し続ける。それは、写真が明示してしまった、私の見ることにおける病である。
[註2]大塚英志『定本物語消費論』角川文庫、2001年。
[註3]その他の著者を以下に記しておく。前川修、長谷正人、小泉晋一、奥山文幸、吉田司雄、今泉寿明、戸塚ひろみ、小池壮彦。
[註4]フロイト「無気味なもの」高橋義孝訳『フロイト著作集 第三巻』人文書院、1969年、327- 357頁。
[註5]ヴァルター・ベンヤミン「写真小史」久保哲司訳『ベンヤミン・コレクションⅠ』浅井健二郎編訳、ちくま学芸文庫、1995年、551- 581頁。
[註6]ジョアン・コプチェク『わたしの欲望を読みなさい ラカン理論によるフーコー批判』梶理和子・下河辺美知子・鈴木英明・村山敏勝訳、青土社、1998年、125- 126頁。