試評 2006.03.01 by 土屋誠一
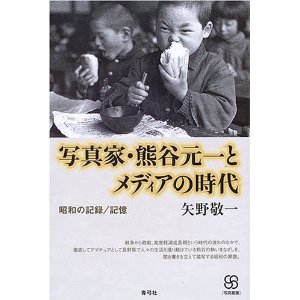
戦前より、自身が住む村の風土を中心として撮影しつづけた写真家・熊谷元一についてのモノグラフが出版された。『写真家・熊谷元一とメディアの時代 昭和の記録/記憶』(青弓社)がそれである。著者の矢野敬一氏は民俗学の専門家であるとのことだが、農村の風土をテーマとしてきた写真家についての書物としては、格好の著者を得たというべきであろう。この書物には、いわゆる「写真家」の「作品」に対する美学的考察はほとんど一つもない。それは著者の専門領域がそもそも目指す必要のない要素でもあろうが、熊谷の写真について考えるためには、写真に対する美学的態度はひとまず留保すべき態度でもある。そのことは後に述べるとして、まずはこの特異な写真家の概要を、振り返っておこう。
1909年に生まれ、現在も健在であるという童画家・写真家の熊谷元一(くまがい・もといち)は、1930年代より小学校の代用教員を務めながら、『コドモノクニ』に投稿した童画が武井武雄[註1]に認められることをきっかけとして、童画家としての活動をはじめる。一方、赤化教員とみなされ、教職を追われたりしながらも、自らの村を記録するという目的で撮影活動を開始する。その写真は美術評論家の板垣鷹穂に認められ、1938年には朝日新聞社から写真集『會地村 一農村の冩眞記録』を出版する。驚くのは、1936年に自身のカメラを購入してから、たった2年で写真集の出版まで漕ぎ着けたということだ。この写真集の刊行は、出版当時から高い評価を得、現在も熊谷の代表作の一つとして位置づけられている。注意すべきは、熊谷はプロフェッショナルの写真家として活動を続けたのではなく、あくまでアマチュアというスタンスを維持していることである。しかしそれは、日本の写真史そのものが示すとおり、また、現在に至る熊谷に対する評価そのものが示すとおり、一義的にプロとアマチュアの腑分けが可能なわけではなく、アマチュア写真家というスタンスが、趣味的な愛好家の域を用意に越えることはしばしばであり、熊谷もそれに例外ではないことは注意しておく必要がある。
次に写真家としての熊谷の活動が表面化するのは、戦後を迎えた後である。主要な写真集は、『かいこの村』(1953年)、『農村の婦人 南信濃の』(1954年)や『一年生 ある小学教師の記録』(1955年)といった、『岩波写真文庫』に収められたものである。とりわけ『一年生』に関しては、近年再編集を加えた書籍[註2]が刊行されていることが証明するように、熊谷の最も良く知られる写真集である。これら『岩波写真文庫』における刊行は、名取洋之助が熊谷の写真を評価したことが大きかったようである。以上に留まらず、熊谷の写真活動は近年も継続的に取り組まれている。
この熊谷のモノグラフは、童画家としての活動には多く触れていないが、写真家としてのそれに関しては、丹念にその足跡を追っている。本書の中心的なモティーフは、写真そのものに対する読解というよりもむしろ、それらのイメージが展開されるメディアとの関わりである。熊谷が童画家としての活動を開始するきっかけが、『コドモノクニ』と武井武雄の存在であったということは先に述べたとおりであるが、そもそもこの「童画」というジャンルそのものが、1922年の『コドモノクニ』創刊当初から深く関わる武井自身によって確立されたものである。このことは、文化的資材を投入すべき価値概念としての「子ども」の存在が意識されるという、まさに近代的市民社会の要請から導き出されるジャンルの成立を意味するであろう。熊谷が童画家としてデビューした1930年代は、都市文化に対する「郷土」や「故郷」に対する関心が高まった時代であるということは、本書の中で指摘されているが、熊谷の童画に見られる「郷土色」もまた、都市に対する「隔たり」としての「郷土」に他ならない。この「郷土」が、『コドモノクニ』という「子ども」を対象とした、雑誌というメディアを通じて生産され、流布されたことは興味深いことである。なぜならば、このような「隔たり」の生産は、熊谷の写真がメディアにおいて発表される写真環境と無縁ではないと思われるからである。
熊谷の最初の写真集である『會地村』は、自らの村を史料の収集を基礎としたテクストによって記述する「村誌」として構想されたものが、作業の膨大さ故に断念されたことを発端としているという。つまり、村の「記録」を、テクストベースの史料ではなく、写真という視覚的な記録メディアによって代理させるということである。写真を通じた「郷土」の発見は、地理的に隔たりのある都市に対して与えられているに他ならない。このような「郷土」に対する視線は、熊谷の写真そのものに折込まれている要素である。この写真集が刊行される経緯として、板垣鷹穂によるその写真の評価と推挽があったということは先に記したとおりであるが、そもそも熊谷の写真が板垣の眼に触れるきっかけは、板垣の著書を読み、あらかじめ影響を受けていた熊谷自身が、撮影した写真の密着プリントを、批評を乞うために板垣に送りつけていたことにある。熊谷が影響を受けたという板垣の論考は、『藝術界の基調と時潮』(六文館、1932年)に所載の「グラフの社会性」であり、板垣の機械主義的美学に基礎付けられた、グラフ形式のルポルタージュ機能が熊谷の写真の理論的背景にあるということである。日本の近代写真史における板垣と言えば、堀野正雄の写真とコラボレートした、『カメラ・眼×鉄・構成』(1932年)が第一に想起されるわけであるが、極論である誹りを恐れずに言うならば、見た目は著しく隔たった堀野のような新興写真と熊谷の「郷土」写真は、実は極めて近似した視線を共有しているとさえ言えるのである。
このことを踏まえて言うと、熊谷が撮影した「郷土」とは、『コドモノクニ』から引き続く、在村の、すなわち「郷土」の内に存在する熊谷という内部の眼が近代的都市によって要請されたのと同時に、熊谷自身もまた「郷土」の外にある近代的都市の視線を内包していたという奇妙な二重性の上に発見された風景である。この二重性は、戦後における熊谷の写真行為とその受容において、特異点をなしているように思われる。ともあれ、板垣の影響から得られた機械的に対象を記録するという熊谷の立場が、名取洋之助によって推し進められたグラフ・ジャーナリズムを経由して、戦後の『岩波写真文庫』に辿り着くのは、極めて理に適った道筋であると言える。
戦後の『岩波写真文庫』における熊谷の『農村の婦人』は、当時の農林省における農業総合研究所の、駐村研究員という立場で撮影された記録写真が基礎になっているという。この研究員という立場への就任は、農村の記録写真集としての『會地村』の評価が元になっており、『農村の婦人』もまた、調査報告しての語り口が色濃い。収録された写真は、被写体の村民たちから一歩引いた視線で撮影されており、被写体もカメラの目線と視線を交わすことはほとんどない。併記された解説文も、村の現状とは距離を置いた記述に終始しており、今日の一般的な感覚からすれば、妥当であるとは看做し難い表現も含まれている。試みに、村の婦人の衣服について記述したテクストを引いておこう。「農村の婦人は貧しい。世間が狭く、苦しい生活をしているから、わずかなことで幸福を感じる。彼女たちの求めるわずかな着物や、労働着すら、満足に与えられないというのが日本農村の現状である。」
この写真集は、現状報告的、もっといえば、望ましくない農村の現状を告発するようなメッセージを発するというトーンが、写真とテクストの組み合わせから顕著に読み取ることができる。これは、グラフ・ジャーナリズムにおける語り口の基本的な形式であるが、果たしてこのようなルポルタージュの客観性、あるいは対象と距離をとるスタンスのみに対して、熊谷の写真が読み取られていたかどうか。戦前の『會地村』同様、発見された「郷土」性という隔たりに対する、ある種のノスタルジーやエキゾティシズムのようなものが含まれてはいなかったろうか。この点に関しては、『農村の婦人』の後書きにおいて、既に現われている要素である。この後書きは、農業経済学者であり、農業総合研究所所長でもあった東畑精一によって書かれているが、ここでは農村の婦人たちの「真の姿をまず描きだすことが何よりも大切である」といったように、客観的な真実を記述する使命が強調されつつも、「彼女たち並びに彼女たちの生産と生活とに対してつよい愛情をもってこそ為し得る仕事である。(・・・)熊谷元一さんはこれらの条件に恵まれたまれな存在である」と、改善されるべき対象である農村に属しつつ、そうであるからこそ対象に愛情を注げる立場にある、熊谷の立場の特殊性が強調されるのである。この「愛情」という情緒性は、熊谷の写真から読み取れる属性では全くない。板垣の教え通り、熊谷の視線は、客観的に対象を記録することに差し向けられている。しかし、主に都市文化の直中にいる受容層は、熊谷の立場から想起されるところの、特徴的な情緒性を要求するのである。
このような客観性と主観的な情緒性との重合は、続く『一年生』においてさらに極まっている。この写真集では、勤務校において熊谷が担任していたクラスの、小学一年生の子どもたちの学校での様子が、丹念に写し取られている。ここでも熊谷の「記録」に基づく眼差しは発揮されているが、とりわけ顕著であるのは次のような組み写真である。撮影されているのは、校医の歯科衛生に関する校内放送を聴いている、教室の子どもたちの光景であるが、数分おきに定点観測で撮影されるショットの集合は、子どもたちが次第に放送による話に退屈し、落ち着きを失っていく様を捉えている。また、子どもたちを捉えるカメラの視点に注意を向けてみると、その多くのショットが、子どもたちと同じ目線の高さではなく、やや俯瞰する視点、すなわち、教師としての、大人としての、さらに言えば、子どもに対して「客体」にある視点で撮影されていることが見てとれる。ここでは、客観的な記録の視線は極まり、子どもの学校での生態を観察することに主眼がおかれている。この写真集の目論見としては、教育心理学的な調査研究の報告、さらには、子どもの躾を考察するための手がかりになるような、成人に対する教育的効果が目指されていることは明らかである。にも関わらず、『一年生』はその当時のベストセラーになり、恐らくその背景に『農村の婦人』と同様の、被写体に対する「愛情」が暗に読み取られていたからではないだろうか。
矢野氏のモノグラフィーでは、熊谷の写真が高度成長期を迎えた後の農村の変貌を記録していくことを記しつつ、同時に登場するテレビという新しいメディアとの関わりの中で、かつて撮影された写真が歴史の記録として、さらには、失われた過去に対するノスタルジーの対象として扱われていく経緯が述べられている。これは換言すれば、熊谷の領分であるルポルタージュとしての写真の機能から、歴史を示す結晶としての写真に変貌するのと同時に、ノスタルジーという甘い欲望を満たす消費材として変貌していることをも示しているであろう。このような写真の意味作用の変貌は、写真というメディアの特質であると一般化することは勿論可能であるし、妥当でもある。しかし、先に述べたように、熊谷の写真行為には、先に述べたような二重性が、あらかじめ折り畳まれていることも事実である。写真メディアにおける機械主義的なルポルタージュの眼差しと、外部として発見される「郷土」を背景とした熊谷という撮影主体の眼差し。この重合のあいだにある隔たりこそが、熊谷の写真の本質ではなかろうか。
ところで、現在の我々において、熊谷の写真の受容は、多くがノスタルジーの対象としてのそれであることは、確認しておくべきであろう。代表作の『一年生』は、再編集された書物として今日手に取ることができる。しかしそれは、初出の刊行当時に目指されていた意図からは離れ、「なつかしの~」という形容がタイトルに付されていることが示すとおり、ノスタルジーの対象として、である。当時を体験していない者は、今日失われているピュアな子どもの姿を、あるべき姿として受け止めるであろう。あるいは、「熊谷元一の写真にはじめて接したとき、不覚にも涙のにじんだ目で自分か仲間がそのなかに写っているんじゃあるまいかと本気で追った」と新版の後書きで記す藤森照信氏のように、同時代を経験した自らの幼年時代を重ねあわせるかもしれない。成人に対して「子供」であること、富裕に対して「貧困」であること、首都圏に対して「地方」であること、都市に対して「農村」であること、といった、あらゆる対立項において「負」の事態を克服されるべき対象として告発することが、ドキュメンタリーに課せられた使命のひとつであるとするならば、一方でそのイメージからドキュメンタリーの機能が捨象され、単独のイメージとして読まれ得るコンテクストに置き換えられる場合、とたんにその「負」のイメージは、愛らしい「子供」であり、麗しき「貧困」であり、望郷の「地方」であり、たくましい「農村」であると認識されるということである。しかし、写真メディアの「記録」という特質を再考するならば、そのような再文脈化の誘惑には注意しなければならない。グラフ・ジャーナリズムの特性である、写真とテクストの併用による情報伝達は、写真メディアの意味作用の不確定性を逆説的に示すものであるが、そのことはさらに言えば、イメージの読解の倫理性が常に問われる局面におかれていることも同時に意味するであろう。矢野氏の著作の副題が示すとおり、熊谷の写真は、当時の報道としてのアクチュアリティから、今日では「昭和の記録/記憶」という歴史における証言と想起のための機能に、その意味作用を変化させてはいるが、もし歴史の記録/記憶から今日においてアクチュアルな教訓を学ぶとするならば、反・歴史的な情緒や美学的態度は慎まなければならない。
[註2]熊谷元一『なつかしの小学一年生』河出書房新社、2001年。