試評 2005.09.23 by 土屋誠一
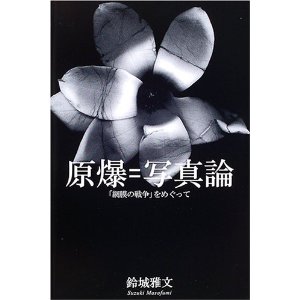
本年6月に刊行された、鈴城雅文による『原爆=写真論 「網膜の戦争」をめぐって』(窓社)を取り上げたいと思う。この書物に含まれる論考の全てではないが、読む者に対して、意義のある思索を導く考察が含まれている。本書は、『写真=紙の鏡の神話』(せきた書房、1985)、『写真=その肯定性(フェミニティ)の方位』(御茶の水書房、1992)に続く、同著者による3冊目の著作であり、前著の末尾で語られた、原爆と写真に関するテーマを引き継いでいる。このたび刊行された著作は、表題の「原爆=写真論」のほか、以前の著作においてもしばしばその名が取り上げられていた、レニ・リーフェンシュタールに関する論考、あるいは開高健の小説についての論考、さらに、写真や、眼差し一般に関する論考などが含まれている。しかしながら、「原爆=写真論」以外の論考は、覚書にとどまっており、論考としてのまとまりを欠いているので、ここでは取り上げることはしない。したがって、本書の約半分を占める論考「原爆=写真論」についてのみ、読んでいくことにしよう。
思えば、原爆をテーマにした写真についての纏まった著作を、寡聞にして聞くことがなかった。これは少し考えると異常な事態であったと言えるかもしれない。なぜならば、表象された原爆を我々が事後的に「見る」のは、必ず写真あるいは映画といった記録メディアを通してのことであることは勿論だが、なによりも我々は既に、原爆が投下された広島と長崎のそれぞれにおいて、土門拳による「ヒロシマ」と東松照明による「<11時02分>NAGASAKI」という、少なくとも戦後日本における、重要な写真家による、代表的な作品を持ち得ているからである。もちろん、それぞれの写真家についての作家論としては、これらの作品がその代表作として分析の対象に上げられて来もしたし、彼らの作家歴においても、代表作の一つとして扱われて来もした。しかし、日本の敗戦を示すのみではなく、なによりも大戦における大量虐殺を示す象徴の一つである原爆が、戦後においてそれを表象しようとした取り組みが少なくない写真との関連において、纏まった形で論じられなかったことは、いささか奇異な感じがしないこともない。もし仮に、原爆を表象しようとする写真について語られることが忌避されてきたとするならば、その原因は、それらが余りにも甘いヒューマニズムに接続されてしまう可能性を充分に持ちすぎてしまうこと故かもしれない。しかし、原爆を表象しようとする写真の問題を回避し続けるならば、それは逆にそのような素朴なヒューマニズムを再生産することに加担しかねないのも事実である。その意味において、この著作は、語られなかった原爆を表象しようとする写真について考察する、意義深い第一歩であると言えるだろう。
「原爆=写真論」は、三章に分かれており、それぞれの章において、山田精三と山端庸介、土門拳と東松照明、石黒健治と土田ヒロミの原爆をテーマとした写真が、論考の対象となっている。この三章はそれぞれ、原爆をリアルタイムで表象した者、原爆を同世代ではあるが事後的に表象しようとした者、原爆以後の世代ではあるが事後的に表象しようとした者、といったように分類できる。
第一章において鈴城は、山田精三と山端庸介の写真から、撮影主体の意図を超越した、外化された「網膜」としての写真の機能を読み取りつつ、「ヒロシマ・ナガサキ」と呼び習わされる「物語」として可視化される原爆が、むしろその本質において「不在/欠如」を招き寄せることから、原爆と写真を等号で結びつける。具体的には、歴史に名を残すことがなかった報道写真家である山田の写真について言えば、原爆の「きのこ雲」を撮影したショットが取り上げられ、撮影した山田自身、その「雲」を原爆投下の原因であることを知らないながらも、シャッターを切ったのではないかという推測が述べられつつ、意味内容を伴うイメージに対する理解と、写真によって表象されるイメージが「得体の知れな」い意味の連関を欠いたものであるという不理解との齟齬が指摘される。一方、原爆投下直後の長崎の様子を撮影したことで名を残す山端については、有名な「支給されたにぎり飯を口にする気力すらない被爆者母子」[註1]を取り上げ、この写真が、悲惨な状況を撮影し、対外宣伝に役立てるようにという軍部の要請に基づき、母子が演出されてカメラの前に立たされている可能性があることを示唆しつつ、にも関わらずプロパガンダの意図に寄与するための構図を台無しにするかのように、背後を横切る男の後姿が写り込んでしまっている事態に着目し、それを写真というメディアの与件である「野蛮」さであると指摘する。写真は、撮影者の目的や技量などを超えて、無差別的にフレーム内のイメージをとらえてしまう。すなわちそれが、写真の「野蛮」の所以である。そして、まさしく「野蛮」な、原爆という未曾有の事態、すなわち人間の了解や理性の閾値を超え、全ての可能性を消尽してしまうそれは、写真の「野蛮」と通底する。以上のような議論が、本章でなされる。
第二章においては、土門拳と東松照明が取り上げられる。先の章における二人の写真家が示していたように、原爆をほぼリアルタイムで捉えた者たちは、写真がその外部を引き込みつつも生産する「物語」を――少なくともその撮影行為そのものに即しては――拒むものであった。しかし、事後的にそれを追認する者たちは、原爆に連なる物語化への欲望を巡って、その写真行為を位置づけざるを得ない。土門の「ヒロシマ」は、まさにその物語化への欲望に、良くも悪くも忠実であっただろう。土門に対しては、写真家としての土門の社会参加における態度を、戦中から「ヒロシマ」の戦後にかけて、一貫して社会「奉仕」というヒューマニズムであると規定し、戦中の翼賛的立場から戦後の社会を告発するリアリズムに政治的立場を転向させつつも、その本質において不転向である、と述べられる[註2]。そして、そのようなヒューマニズムに立脚して撮影された土門の写真は、「ヒロシマ」の「事実」の告発として、戦後の大衆に対して提示される。まさにこの告発という目的に基づいた整合性は、「物語」の再生産に寄与する。一方、東松の「<11時02分>NAGASAKI」に対しては、その出自を土門の「ヒロシマ」に対するアンチ・テーゼであると位置づけつつ、「ヒロシマ」に見られたヒューマニズムを、被写体を「モノ」化することで退ける一方、その「モノ」化の帰結として、イメージを「審美」化する撮影主体の「想像力」によって、結果的には別の「物語」に接続されてしまう、と批判的に述べられている。いずれにせよ、写真の外部に「リアリズム」=「ヒューマニズム」を設定するならば、それを肯定・否定しようとも、ナラティヴの再生産に帰着せざるを得ない、ということが述べられているのだと言えよう。
第三章において、より現代的な原爆を表象しようとする写真が対象とされている。ここで扱われる世代においては、原爆の痕跡としての「記憶」が、時代的に、また、その時代が織りなす風景において、忘却されつつあるという認識が出発点となっている。具体的に提示されるのは、まずは石黒健治の「広島HIROSHIMA NOW」であるが、石黒は、あからさまに原爆を想起させるケロイドのような痕跡と、撮影された時点における現在のとりとめもない風景を併置させることによって、原爆の安易な物語への回収を拒絶していると評価される。手法としては、写真のフォーマルな表象への回帰ともいえる「コンテンポラリー・フォトグラフィ」(あるいは日本の文脈に沿うならば「コンポラ」と明確に言った方が良いと思うが)的スタイルが選択され、「HIROSHIMA NOW」におけるイメージを構成している。この物語化への拒否は、先の山田や山端が得たような写真の「得体の知れなさ」に、石黒の写真を近似させつつ、「記憶」の「いま」現在の有り様を映し出すことに結実し、このコンポラ的スタイルはまさにそのための「方法」であると述べられるのである。もちろん先の時代認識のように、「記憶」の「いま」に原爆の痕跡がさほど残っていないとはいえ、むしろその「見えがたいものの見えがたさ」が、すなわち表象することがきわめて困難であるであることの表象が、ここでは獲得されている、と述べられるのである。一方、対極的な例として、土田ヒロミの「ヒロシマ」シリーズが扱われる。土門の「ヒロシマ」が、社会へのアンガージュを目的としながら、結果的には土門による「物語」の再生産(しかし、それが物語に対する大衆の欲望の公約数であるにせよ)にしかなり得ないのとは異なり、被爆経験者を取材するプロセスそのものを「記録」し、原爆の「モノ」としての痕跡をその表層において「図鑑的」に「記録」し、土田は、ヒロシマに対してあくまで「他者」である主体にとどまることによって、物語化を拒否するのだと評価されるのである。
さて、それではなぜ「原爆」と「写真」なのか、そして、原爆を表象しようとする写真は、現在においても可能であるのか。鈴城が本書においてマルグリット・デュラスの「ヒロシマ・モナムール」におけるあのリフレインを通奏低音としているように、可能性の消尽である原爆を、いかに写真は表象し得るのか、あるいはし得ないのかという問いが、ここで問題になる。この原爆と写真の親和性は、両者ともに絶対的な他者として立ち現れる点において、結びつけられる。本書における写真家は全て、原爆の、逃れることのできない表象不可能性という事態において、それぞれの写真を残したと言えるかもしれない。第一の世代は、原爆に直面した際に引き起こされる「得体の知れなさ」という反応において、写真を撮影した。次の世代は、本来表象し得ない原爆を、原爆から導きだされる物語の方へと密輸入しつつ、代補的に原爆の表象という幻想を生産した。そして、最後の世代は、表象の可能性をそもそも断念した地点から出発しつつ、その断念そのものを表象することで、逆説的に表象の空隙としての原爆を示唆しようとした。しかし、原爆が時代の推移の過程において歴史化され、そのトラウマさえ歴史における一つの知識として格下げされている現在、原爆を表象しようとする行為はいかなる意味を持つのか。一見正しい立場であるかのような、先の最後の世代でさえ、原爆の痕跡が例えば生存した被爆者の身体に刻印されているという事実を担保として、その表象不可能性に価値を与えていたのではなかろうか。今日においては、例えば笹岡啓子の「PARK CITY」のように、そこに表される痕跡は、平和記念公園のような二次的なメモリアルでしかあり得ない――つまり、原爆のインデックスとしての痕跡が失われ、間接的な資料体に基づく、歴史上の事実としての原爆でしかあり得ない。かつては、表象しようとする対象の事実性に基づいていたのに対し、今日の表象不可能性は、そのような基礎付けを欠いた、文字通り不可能なものである。語り得ぬものに対して断念することは、裏返しのロマンティシズムを引き寄せがちであるが、そもそも断念など存在せず、単に「ない」という欠如から出発するならば、写真は何を捉えるのであろうか。明確な回答を出すことは困難であるが、一つだけ、次のように言えるかもしれない。当たり前ではあるが、もし忘却に抵抗するならば、不断にそれを想起することが要請されるだろう。この想起を、写真行為と等号で結ぶならば、写真は事実性の記録ではなく、ナラティヴの源泉でもなく、また不可能性の謂いでもなく、文字通りの「原爆=写真」という事態が到来するのではなかろうか。
最後に、別の視点から、補足的に述べておきたい。本書がメディア論を偽装した原爆についての写真評論ではなく、あくまで個別的な作家および作品について言及するという過程を伴ったテクストであることは、決して軽んじるべきではない。評論という行為が、一般性に回収し得ない残余を読み解く作業を伴わないならば、そのような評論は結局のところ「見る」という行為を壊死させるであろう。その意味において、この「原爆=写真論」が問うている、「見る」ことと「語る」こととの可能性についての考察が実践的に示しているように、評論という行為もまた、この可能性についての考察の実践でなければならない。
[註2]鈴城は、土門の戦後におけるリアリズムの主張に対して、次のように言ってのけている。「揺るぎないヒューマニズム(土門はそれをリアリズムと呼んだようだが)」。さらりとした一言だが、土門のリアリズムを「ヒューマニズム」と等号で結びつけるという読解は、きわめて的確な指摘であるように思われる。