試評 2004.05.26 by 土屋誠一
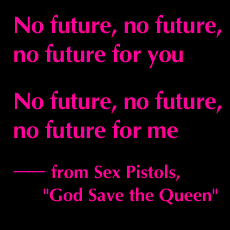
あなたに未来がないのと同様に、私にも未来はない。勿論、これは、「未来」そのものの到来が、永久に訪れないということではなく、私たちが肯定的に捉えうる「未来」は訪れないということだ。しかし本当は、私たちが望むと望まざるとにかかわらず、未来は訪れる。私たちは、ヴァルター・ベンヤミンの「歴史哲学テーゼ」で語られる、歴史の天使のように[註1]、「進歩」という肯定的価値概念を付与された強制によって、不可避的に未来へ、未来へと送り込まれるのだ。資本主義における再生産のメカニズムは、それゆえに何ら反省を要請しない。私たちは単にそのメカニズムを反芻し続ければよい。そこでは、あらゆる差異や権力構造もまた、現状維持のまま前進し続け…、いやむしろそのような構造に対して、無反省であったほうが、効率がよい。しかし、そこで抵抗を試みることは、いかなる方法によっておこなわれるのであろうか。また、その抵抗は、本当に可能であろうか 。
1960年代末におけるロック・ミュージックは、ヒッピーイズムと連動することによって、ある種の反社会的姿勢の象徴的役割を担う。しかしそれと同時に、例えばジム・モリソンが歌う「ジ・エンド」における終末論的なヴィジョンは、後にフランシス・コッポラの『地獄の黙示録』に見られるように、ヴェトナム戦争の軍事テクノロジーと表裏一体をなし、60年代のロックが持つ危うさを、的確に表出していたように思われる。フリードリヒ・キットラーが的確に指摘するように[註2]、戦争テクノロジーとロックの親和性は非常に強い。ウッドストックが象徴するような野外フェスティヴァルには、大群衆に分け隔てなく最良の音質を供給できるだけの、高性能のPAシステムの導入が必要であったはずである。勿論ここでは、ジミ・ヘンドリクスが激しいフィードバックの中で奏でる、アメリカ国家の大音響もまた、想起すべきである。フィードバックやディストーションのかかった強烈な大音響は、端的に言っても、爆弾のような戦争テクノロジーがもたらす暴力を思い起こさざるを得ない。また、ステージ上で繰り広げられる破壊的、否定的、反社会的音響にもかかわらず、コンサート・ステージという舞台上にある、ロック・スターという中心点は、象徴的な超越者としてのポジションを確保してしまう。それは、ナチズムがヴァーグナーから読み取ったような、群衆対超越的一者という構図、プロパガンダのテクノロジーを背景にした政治的総合を、無意識的にであれ、反復するのである。
上記のように、60年代末に起こったロックの可能性の限界は、70年代に入り、ロックの自己言及化という手段によって、捉え返される。クイーンにおけるロック・スターのキッチュとしての反復、あるいはグラム・ロックにおけるロック的ヴィジュアルの過剰化を想起して欲しい。つまり、音楽的可能性を消費しつくした上で、その可能性の一覧を、その都度ブリコラージュすることによって、延命を計るということであったはずである。しかし、自己言及的な反復行為は、それを行う主体の分裂を引き起こさざるを得ない。それは例えば初期のロキシー・ミュージックの面々が纏っているファッションが、それぞれ様式的一貫性を全くもたないという点であるし、なによりもデイヴィッド・ボウイが「トム少佐」、「ジギー・スターダスト」、「ダイヤモンド・ドッグス」、「シン・ホワイト・デューク」といった複数の主体を、アルバムごとに演じ分けるといった事態が、それを良く示しているであろう。ここで見られる、ロックの自己言及性、あるいは反復性は、そのジャンル的特性に対する、批判的な再検討であったはずであるが、それはむしろ、ロック・スターの神話化を強調することにもなる。
そして、パンクの時代が訪れる。私はここで、パンク・ロック、とりわけセックス・ピストルズとジョニー・ロットンについて述べようと思う。しかし、なぜ四半世紀も前のスタイルについて、今更ながら語ろうとするのか? セックス・ピストルズといえば、ちょっとしたロック愛好者でさえも、うんざりするほどの回数、その音楽を耳にしてきたバンドではなかったか? 現代のこの時において、エレキギターを構え、”anarchyyyyyy!!”と叫ぶならば、質の悪いジョークとして捉えられるか、時代錯誤な輩として敬遠されるのが関の山であろう。しかし、1970年代という、革命の時代も過去のものとなり、遅れてやって来たとしか言い様のない、このパンク・ロックの象徴的バンドのその本質は、既に消尽されてしまったのであろうか。ここでは、二重化された「遅れ」を担わざるを得ない。ひとつは、パンクが本質的に抱えている遅れ、すなわち60年代末に頂点を迎えた革命期からの遅れ、或いは隔たりであり、もうひとつは、21世紀初頭を(まさに望むと望まずとに関わらず)迎えてしまった現在から測定されうる遅れである。しかし、そこに含まれていた可能性は、革命を夢見ることも適わず、極端化するならば慢性的シニシズムやニヒリズムに向かわざるを得ないようなこの時代において、再考されるに似つかわしいスタイルではなかろうか。
サイモン・フリスは、パンクの特徴として、それがラヴ・ソングを必要としない、初めてのポップ・ミュージックであるという点を指摘している[註]。ポップ・ミュージック、とりわけロックは、たとえ純粋な求愛を歌い上げていたとしても、本質的に性的リビドーの充足に向けて発せられたものであると言える。それは、エルヴィス・プレスリーにおいては、その腰使いにおいて、あるいは、ヘンドリクスが股間の辺りで身体に対して垂直に立てるギターにおいて、シンボリックに表されていたはずである。ジェンダーの差異において、受容のあり方に相違があるにせよ、彼らの崇拝者は歌詞、サウンド、ヴィジュアル・イメージが渾然一体になった、その性的な感覚を、そこに嗅ぎ取っていたはずである。そしてまた、その性的リビドーの消費形態は、ロックの産業における消費形態と一致している。セックス・ピストルズは、そのバンド名にもかかわらず、フリスが指摘するとおり、確かにラヴ・ソングに該当するような曲が存在しない。音そのものに関していっても、特にロットンの声は、”baby”と呼びかけるような声からは程遠く、がなり立てたとしても、男性的な恫喝というよりも、むしろヒステリー的な痙攣に近い。それは、リビドーの開放、エクスタシーというよりも、リビドーを解体しようと差し向けられたヒューモアの表明である。
このシャウトの象徴作用の差異は、彼らのマネージャーであったマルコム・マクラーレンの出自を経由して、シチュアシオニストの「転用」の技法へと接続することが可能であろう。しかし、そのような価値の転用よりも、カン(CAN)のマルコム・ムーニーを経由したと言われるロットンの声[註4]は、あくまでヒューモアとして捉えるべきである。具体的には、”R”の発音における巻き舌、吐き捨てるような語尾の切断、しゃくり上げられる語尾、不安定な音程、そしてなによりも、ロットン自身のロック・シンガーにあるまじき線の細いテノールを指摘する事ができるだろう。これらはすべて、ロックにおける象徴作用に対する、ヒューモアによる脱臼である。ロットン以前の歌唱法は、歌詞の意味作用を、そこに込められたメッセージを正確に、またはシャウトなどの装飾を交えて演劇的に表すのに対して、ロットンのそれは、メッセージの伝達効率を阻害することに寄与する。言語における意味作用を破棄された声は、音楽の純粋性という意味においては、(パンクの楽曲構造における、スリー・コードへの還元ということも含めて)グラム・ロックにおけるマニエリスティックな自己言及性を超えて、形式化への意思が反映されていると見ることもできるかもしれない。しかしそこでは、コード化された言語作用と、音声としての声の両極を行き来する、ある種の中途半端な場所に滞留する。そのことは、絶えず自らの位相を、定位することなく移行させ続ける、闘争の技法ではなかったか。ダダ。
[註2]フリードリヒ・キットラー『グラモフォン・フィルム・タイプライター』石光康夫・石光輝子訳、筑摩書房、1999年。
[註3]サイモン・フリス『サウンドの力 若者・余暇・ロックの政治学』細川周平・竹田賢一訳、晶文社、1991年、p.286。
[註4]フリスは、ロットンの発音を労働者階級の、そしてまたサッカーの応援歌のそれを、直接歌唱に持ち込んだと指摘している。前掲書、p.195。