イベント:Sato Makoto/佐藤 真 “Self Projection”
Information

SATO MAKOTO 「SELF PROJECTION」
2002年3月2日(土)
協力:坂川直也
映画監督・佐藤 真が自身の作品を自らの「手」で解体する一日限りの「投影会」。会場にて佐藤監督撮影の「東京写真」も併せて展示。
上映時間
1.
13:00 – 13:25
「市場最大の作戦」(約25分)
16mm、ビデオプロジェクター、テレビ
2.
13:35 – 15:05
「写真で読む東京」(約90分)
16mm、8mm、ビデオプロジェクター、テレビ
3.
15:15 – 16:00
「我家の出産日記」(約45分)
8mm、ビデオプロジェクター、テレビ
4.
16:00 – 16:40
監督トーク
上映内容
ビデオ撮影:加瀬澤充
ビデオ編集:笹岡啓子
ズッコケたり斜めに構えたりが私の性癖ではあるが、最近とみに「映画」からズレ始めている。「SELF AND OTHERS」で憧れの写真家と親しく対話をする機会に恵まれたり、「まひるのほし」から「花子」への一連の「境界線上芸術」への関心を通 して、多くの現代アートの作家と出会って挑発された影響が多分にある。ただし、決して映画という制度を変革したり、映画界の偏狭さを揶揄しようなどという野心は微塵もない。ただ、ズッコケついでにたまには変わったこともやってみたいと思ったまでのことだ。
なにしろ、仕掛け人が敬愛する写真家・北島敬三である。それもまさかと思った場所で偶然出会った立ち話で、自分たちのギャラリーの一周年記念に上映会をやりませんかとのお誘いである。ただでさえ退屈な拙作を、今後ひとつの伝説を生み出すに違いない「フォトグラファーズギャラリー」で上映するだけでは、せっかくの自主ギャラリーの名折れとなる。そこで思いつく限りの映像てんこ盛りの投影会を苦し紛れに思いついた。格好だけはインスタレーションという代物だ。実は、これが一度やってみたかった。かくして、酒を飲んだ勢いで、随分と大々的にやるはめになった。
簡単に言えば、自分の作品に未編集素材を投影して解体してしまおうという映写 会だ。体の良い教養番組になり下った「写真で読む東京」(NHK・ETV特集)を、ほとんど使い切れなかった16ミリフィルムの風景ショットと8ミリフィルムのメーキング(この素材をテレビ放映するしないでNHKのプロデューサーと大喧嘩になった)とで完膚なきまで自己解体してしまおうとフツフツと悪意が首をもたげてきた。このテレビ作品は、私の東京論のひとつの一里塚のつもりだったのが、NHKの老若男女に分かりやすくという愚民思想の壁によって何重にも包囲され、後退戦を強いられた悔恨の思いがある。これを機に未編集素材をいじって、再起を期するよすがとなればと思っている。
「市場最大の作戦」は青森県の県立美術館整備室が主催の「アートキッズワールドあおもり2001」で作った映画である。私は、この青森で、北島一派と呼ぶべき、企画者の笹岡啓子や坂川直也と出会って、連日、酒を飲み明かしたのだ。このアートイベントで私の担当は「駒どり親子の大冒険」と題したワークショップであった。青森市内の小学生たちと駅前市場を舞台にして16ミリ映画を制作する。そこでヤノベケンジやPHスタジオが造りあげた現代アートを舞台に、子供たちが時に人形やモデルに扮して駅前市場を疾走するというストーリーを思いついた。もちろん、そのスピード感は「駒撮り」によって簡易なアニメ仕立てで造形される。そして、上映会は、駅前広場に造られたリンゴ箱コロシアムの中で、参加した子供たちの生演奏による伴奏つきで中野渡尉隆の指揮の下に上映された。この映画「市場最大の作戦」を「駒どり親子の大冒険」のメーキングビデオと同時平行しながら上映してしまう。
また、テレビ東京「ドキュメント人間劇場」で放映した私の私的ドキュメンタリー「我家の出産日記」(二人目の娘・萌の出産ドキュメンタリー)と極私的8ミリ映画「我家の出産日誌」(一人目の娘・澪の出産記録映画)をインスタレーション的に同時上映もある。
なにせ、名うてのフォトギャラリーでの上映会である。純白の壁を貧弱な映写 だけで埋められるはずもなく、私が撮り散らかした写真も展示するはめになった。最早、毒を食わば皿までの心境である。実は、乏しい問題意識と貧相な写 真テクニックで撮りためた「東京写真」がサービス版のカラープリントでゴミの山ほどあるのだ。しかし、もしかすると北島一派の鋭い批評眼によってそれらの写 真群は一蹴され、申し訳程度に数枚貼り出されるだけなのかもしれない。だが、それでも私にとっては立派なはじめての「写 真展」である。
なにしろ、「SELF PROJECTION」である。場の雰囲気と観客の怒号やスタッフの罵声によって、私のささやかな野望は見事に打ちくだかれるかもしれない。また、図に乗って、自らの映像作品を解体するだけでなく、すべて何やら訳の分からない<イメージの残骸>の山を築くだけになるかもしれない。あとは、運を天にまかせるしかない。ひな祭りの前夜の余興になればもっけの幸いである。
上映プラン
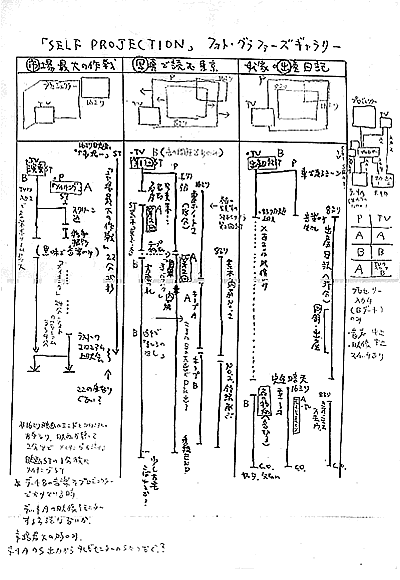
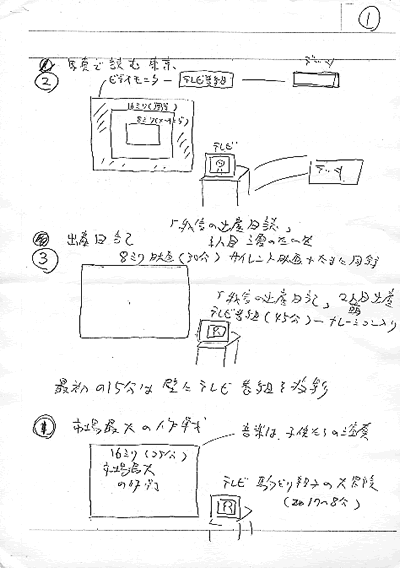
上映作品を決め、おおまかな
投映案を検討。
↓
使用機材の検討。
↓
上映順、上映時間の検討。
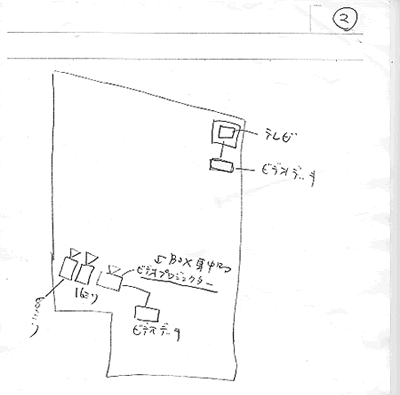
実際は少し違う配置。
アーティスト・トーク
今見ていただいた『我家の出産日記』っていうのはうちの家族にとってはこんなもの撮っていいんだろうかと思うところもありまして、本当はあんまり他人には見せないで自分のところで取っとこうと思ったんです。今日はあんまり私の家族の知り合いという人がいないんで大丈夫かと思うんですけど、良かれと思って「見ましたよ」とか決して言わないで下さい(笑)。家族に秘密で、「ちょっと頼まれて新宿で上映会があるんだ。」と言ったんで、良かれと思って言われるとですね、「なに、あんたそんなもの見せて。」と言われると困るんで、それでつい僕も、我家の家族に、上映することを言うきっかけを失ってですね。また今回も黙ってようと思いつつ(笑)。
たぶんどなたも結婚されたり、子供たちがいらっしゃると、そういう時期があると思うんですけども、誰にでもポワーッとした時間がある。我家でももう、ああいう時間は考えられないんですよね。別 に氷のような時間ばっかりではなくて、たまには雪解けの時もあるんですけども、やっぱりああいう時間というのは全くなくて、僕もちょっと見直すと実に不思議なんですけども。

『我家の出産日記』というのを撮ってる時に僕は『阿賀に生きる』というのを作ってたんです。新潟でずっと映画を作ってまして、実は僕にとって一番苦しい時期、つまり撮影が2年目過ぎて、編集に入る時なんですね。だいたい何も見当がつかない映画で、編集に入るということだけ決まってるんですけども、一体これで映画になるんだろうかと思いつつも、スタッフ7人も抱えて一緒に2年も生活して、3年目を迎えようとして、もういまさらやめるとかって言えないというような時期に、うちで子供が生まれるということがあって、1ヶ月だけスタッフを離れて東京で暮したんです。『阿賀に生きる』という映画をご覧にいただけた方は分かると思うんですけども、その時まで僕は、ずっと新潟にいましたので、たった2年なんですけども、あの山の中のじぃちゃん、ばぁちゃん達の田んぼの手伝いをしながら映画を作ってましたので、その頃はバブルだったんでしょうけども、僕はそんなことは一切知らずに山の中で暮してたんですね。じぃさん、ばぁさんと暮して毎晩、酒飲んだりなんかして。
そんな時に家に帰るということも新鮮だったんですけども、東京の町がすごく新鮮だったんですね。特別 何かあるわけでもないし、特別な場所でもないけども、なんかすごく新鮮で、それに子供が生まれるっていうことがあって、どうしても無性に映画を撮りたくなって。でも、ビデオではダメだと思ったんです。ビデオはもちろん持っていたんですけども、ビデオで撮ってもつまんないと思って、なぜか8mm映画を撮りたくなって8mmで撮ったんですね。

今、見ていただいた通り、助産院に分娩室ってあるんですけども、なんせ8mm映画で撮ってますので、普通 のこんな(蛍光灯)ライトでは映らないわけですね。で、アイランプを3灯吊ったと思うんですよね、助産院に(笑)。だからライティングは完璧なんですよ、生まれた瞬間なんて。逆光までちゃんとあたってね。それでしかも、同時録音できるマグネコーティングがついてるフィルムが確か4本(約10分)ぐらいしかなかったんで、肝心の出産のシーンをワンショットで入れる為にどうするかってことしか考えてないんですね。「わぁ、入った、良かった!」ってことしか考えてなくって、分娩台の上で妻が苦しんでるとか何とかっていうことは目に入らなくて、ただただどうやって出産のシーンをワンショットだけに入れ込むかっていうふうにしか考えてないもので、そういう私の姿を見て、私の連れがいたく失望しまして「あんたはほんとに人でなしだ。人の気持ちも痛みを考えていない。」っていうふうに言われまして。それ以来、随分、薄氷を踏むようなというか、氷のような暮しのキッカケになるわけですけども(笑)。まあ、どなたもそういう経験がたぶんお在りになるんじゃないかと思うんです。
そういう間に撮った素材で、一度ちゃんといじろうと思って何度か編集をしてまして、サイレント映画にしてるんです。それで、僕にとっては実は終りなんですよね。あの、僕にとってはホントは北島さんとの話が無ければずっと上映するつもりがなくって、僕が死んだらきっとこの映画は公開されてもいいんだろうなっていうふうに思ってたところがあるんですよね。そういう映画があってもいい、僕が例えば寝たきりになったら再編集してもいいかなとかね。だからいったん自分の生きてる現在の時間と違った所に行った時にこの場所に映っている私っていうか、我が家の日常っていうのは、私であるけどもとても遠いようなものとしてあるような気がして、ちょっと時間をおいていじったり見直したりする。
そして、たまに何度か本当にどうしてもこれ大事だなと思う時にだけ上映をする。新しく自分の映画を作る時だけに、何人かの仲間にこっそり見てもらったりなんかしてきたんです。ちょっと言い訳がましいですけども、やっぱりこの『SELF PROJECTION』っていう形でなんかやれって言われた時に、この作品は一度きちっと見てもらう必要があるなと思って、少し覚悟を決めて今日は見ていただいたということなんです。
3つのプログラムを今日は見ていただいたんですが、先程、午後に上映会をしたんです。それで今が2回目なんですけども、全く違うんですね。どっちが良いってわけじゃなくって、まぁ、夜の方がいいんですけども(笑)。それは1回目よりも2回目の方が進歩するというか変容あるものなんですね。もうこれは今日だけで終りですので、もう二度と同じものは見れません。
やっぱり映画の編集とすごく似てるし、アートとすごく似てる感じがしてるところがあって、いくつかの映像とかいくつかのイメージとかを重ねる訳ですが、それぞれの根拠があってそれぞれのものがあるんですけども、それを論理的に繋げるとなんかこちらの論理で納まってしまって。どうしても映像をプロジェクションするには論理で固めていくんですけども、1回目は論理でこう一生懸命やって、やっと機械の操作が慣れて、やっとできた。それで、2回目は、ちょっと合間にお酒を飲んでしまったっていうのもあるんですけど、もうどうでもいいような気分になってきて、めちゃめちゃにやったら、ある偶然で、理屈では合わないのに、ぶつかったり反発をしたりするっていうことがあり得て、「あ、それはそういうもんなんだ」っていうふうに僕は思ったんです。
僕の写真も貼っていただいたり、それもめちゃくちゃな写 真でよくこんなものをセレクションしていただいたなと思うんですけれども、これも大きな意味で<東京>というテーマから来ていて、結局、何かはっきり確固たるものがあるわけじゃなくて、とても曖昧なものの象徴みたいなものとして、<東京>というものへの関心がある。私はそこに生きてるはずなのに、私がそこにいなくちゃいけない理由がほとんどない。そこに根拠はほとんどないのにそこにいる、というような町として、この僕が生きてる場所とこの場所と、そしてこの僕が撮った写 真とか、今日見ていただいたものもありましてですね、そういうつもりで実は同じような通 底したテーマがあるような気が僕はしてます。
青森で撮った『市場最大の作戦』も同じなんですね。青森らしさなんてことは全然僕は興味は持ってなくて。僕は、実は青森県生まれなんですけど、全く青森県とは縁がなくて、2歳までしかいませんでしたから、津軽弁はもう一言もわかりません。青森の言葉は本当に外国語で、何言ってるかちっともわからなくて、そのわりには青森の人は暑苦しいくらいに「青森県出身ですね。」と言われるんで、「うわぁー、これは嫌だなぁー。」と思ったりなんかするぐらいに青森県人は県人意識が強い。そうした強力な郷土意識と、私のいい加減な血筋というか根無し草のあり様がどうしても切り裂かれている。

子供たちと町を歩いていても、今日見ていただいた『市場最大の作戦』で夜の町を疾走したのも、青森らしい場所ではなくって。青森ってのは本当に、駅前がこう、すぽーんと空洞化していましてですね、かつての繁華街がどわっと廃墟になりかけている。そんな場所がものすごくおもしろくって。青森県の人にとってはなんだこれはっていうようなものなのかもしれませんけど、そういう空洞を見るとやっぱりまさに東京と同じだなぁと思ったり、それで無性にカメラを回したくなったりするということでしてるんですね。掴みようが無いものとか掴もうと思っても掴めないものというようなものをどうにか撮りたいなというふうには思っています。
今日の企画も笹岡さんとか坂川さんとかフォトグラファーズギャラリーのみなさんにやっていただいたんですけども、写 真家の人達も写真という表現の中で掴もうと思うとスルリと抜け落ちてしまうような掴み所が無いところをどうやって定着をさせていこうかっていう問題意識のような気が僕はしましてね。
そういう写真家が僕はすごく好きで、どうしてもそういう系統の<食えない写真家>っていうかですね(笑)、右から左へパパパッと物事を捕まえて、パパパッと言葉をかぶせて、ポッと商品にするんじゃなくて、いつも掴み所の無いようなだらっとしたものを捕まえてしまうもんだから、どうしようもなくって、ただポンッと置いて、それが商品にもならないし、かといって時間をおかないとなんとも料理しようがないものを抱えていく、決して世渡りが上手くない生き方の中にこういう風景とか素材とかいろいろフッテージの問題があるような気がして今日いろいろ見ていただいたものをいろいろ考えまして、ごちゃまぜにして投影したということです。まぁ、お酒でも飲まないとなんとも話ができないかもしれませんが(笑)。ということで最後までありがとうございました。
上映作品Q&A
佐藤A:あー、それね、あんまり意図ないんですよ(笑)。たまたま子供だったんですよね。そんなに僕、子供好きじゃないんですよ、いやホントに。かわいいとは思いますけども、自分の娘も映像の被写 体として見るとやっぱりすごく不思議な存在だなっていう感じしますよね。だからただかわいいというふうにはあんまり思わないのがいけないお父さんなんでしょうけども(笑)。
会場Q:方法としてマルチプロジェクションという形で、しかもいろいろ8ミリでやったりモニターでやったりという形で、自分が作られた仕事をもう1回こう・・・いわゆるサンプリングとはまたちょっと違った形で、ご自分の仕事をもう少しいろんな形で構成されるというのは、とてもおもしろいと思いましたし、写 真の問題とも深く関わっている訳で。なるべく物語っていうのをですね、大きな物語を画像でもって描いていく訳なんだけども、そういう時代がもうなくなった時に、我々が現実というものをどういうふうに映像でもって物語化していくかという、非常に多義的なですね、思想的な物語が同時に進行していくというところが今回のプロジェクションのおもしろかったところなんですけども、それは意図されてのことなんでしょうか?
佐藤A:いや、そう言っていただくとね、ちゃんと最初から意図したような、アレなんですけども(笑)。ただ多義的になることでその多義性が豊かになるのか、めちゃめちゃになるのかっていうのは実はものすごく微妙な問題でね。映画っていうのは単線的というか線路がいっつも一つなんですよね。その中で時間、つまりスクリーンっていう一つのフレームの中でどういう時間をその中に呼び込むのかっていうことをずっと考えていて。僕もそれなりに映画を何本か作りながら考えざるを得ないんで。四角で囲まれたひとつの世界を見るフレームみたいのが確固としてあるんですけども、どうも一つの四角のフレームでは見えないものがあるなという感じがあるんですね。それはアートとかいろいろな別 の表現ではそういうことは当然なんだけども映画っていう制度の中ではやっぱり一つの四角っていうことを外すのがすごく難しくて。理屈っぽい言い方するとやっぱりいつもこのプロジェクションをやってる時もひとつの四角なんですよ。ここのスクリーンがあってここにこういう画面 があって、こういう画面があって・・・っていう四角なんですよね。それがもっと豊かに多義的になるにはどうしようかなと思って。僕にとって発見があったのは、例えば1回目は、ちゃんとフレームの中で全体のバランスがあったんですよね。2回目は実は、その間にちょっとどうして行かなくちゃいけない飲み会があったもんで、どうしても行かなくちゃいけなかったもんで、どうしても飲んでしまったもんでですね(笑)。だから、少し酔っ払ってどうでもいいような気分になると、意外とその気分自体が多義的なんですね。だから今おっしゃった意味でいうと、自分が意図したものが多義性の豊かさになるのではなくて、意図しないものとか偶然であるとか、その辺で蹴つまずいたということが実は大事なことだと思うんですね。今、言われたことですごくよくわかるのは、写真という表現はそうした偶発性に随分近いのかもしれないなという気がね。最終的に編集で仕上げる時にはすごく意図があるんですけども、撮る瞬間というのは、あまり意図するとダメで、蹴つまずいたり失敗したりとか意図や作家性なんかどっか行っちゃったっていうことの方がむしろ写真にとってすごく大事でね。そのことが映画にはなかなか難しいんですよね。映画のフレームにはいつも意図があって、そりゃ一生懸命がんばって、外すのが上手いカメラマンもいっぱいいるし、映画の既成の審美観から外れることで勝負をしてる例えば田村正毅みたいなカメラマンもいて、それはそれで、すごくおもしろいなと思いながらも、でもやっぱり映画はフレームでね。それはまぁ、ひとつの制度でしょうがないんですけども。でもそれとは違うものがあるような気が僕はしましてね。結局『SELF PROJECTION』は1回で終ってしまうんですけども、1回で終ってしまうということの中にヒントかなんか別 なこともできそうな気もしてくる。まぁ、こういうこともあってもいいのかなという程度のね、これで何かができるというわけではないというような気もします。それと、やっぱりこの狭さっていうのがものすごく大事な気がしますね。映画館としては成り立たないですもんね、ミニシアターだってこれじゃ30も入らないですもんね、席を置いたら。10人のミニシアターっていうのは。しかも新宿2丁目の10人のミニシアターで何を映画やるんだっていうことになるんで(笑)。だからこの狭さというこの限定されたいくつかのマイナス要素が逆にプラスになるような気がして、僕にとってはとっても刺激的だったんですけどもね。

会場Q:今のフレームと制度の話についてなんですけども、映画ってこうあらゆることをやりつくしたと言われるんですけども、なかなか映写 機を振ったという映画監督はなかなかいないんじゃないかと思うんですけど。それはやはり新たな映画的快感というのがあるんでしょうか?
佐藤A:僕、最近どうも、現代アートの人達とつきあう機会があって、「俺も振ってみたいな。」っていうその程度なんですよ(笑)。よくやってるでしょ、こういうのって。それで、「俺だって振れるよ、そんなものは。」っていう。つまりね、振るっていうこと自体にはあんまり意味がないんですよね。例えば、アートのステージだとやっぱりどう見せるのかっていうことに関してすごく意識があって、そのためのテクノロジーに関しては相当、研究もしてるし、すごい蓄積もあって「いやぁ、すごいテクノロジーですね。」っていうところがひとつの評論のステージになって、そうなると僕なんかは映画屋として、「へぇ、テクノロジーはすごいけど、中身はカスだ。」という感じが実はあってね。中身に力がないとやっぱり振る意味がないという気が僕はすごくあって。この投影会の3つのプログラムとも実はずっと振ろうと思ってたんですよ。だけど、振っていいのは『写 真で読む東京』だけで『我家の出産日記』は振っちゃいけない。そういう発見があったのね。 で、サイレント映画で音が無いっていうのも、これはこれでいいんだっていう。退屈だっていうのも大切なんだ、つまりね、なにか全部いくつもの要素が重なれば、物事が複合化していったり多義的になるっていうんじゃなくて、逆にいうともうこれしかない、これしか映ってないっていうのもそれはそれで見る側にとって別 な意味での多義性を内包するんです。足し算の物事の考え方と、引き算の物事の考え方っていう両方あって、それを昨日から、この壁というスクリーンでいろいろ考えてみると、意外とそのいっぱい機械があればできるという問題ではなくて、むしろあまりなくてもいいという、気がしましたね。それは自分の映画を作ることにとってもそうだし、例えば、映画がどこかで上映されてた外で戦争が起きてるとか、何か外で喧嘩が起きてるとかっていう多義性を常に映画という表現も孕んでるわけじゃないですか。その中でやっぱり、フレームの中だけの世界だけども、外の世界の影響を受けながら、それをどうやって対話をしていくのかってやっぱり作り手の側には常に問われている。決してフレームの中で自足して、それが不変のフレームであるっていうふうにはやっぱり思わないですよね。こういう投影会も別 にとんでもなく新しいことでもないし、どちらかというと、全く古めかしいことであるし、ここでやったからっていって映画の制度に対してのある批判とか解体ができるとはちゃんちゃら思ってません。なにか手探りでやってみたに過ぎないんだけれども、紛れもなくこれは映画なんですよ。映画っていうか映写 なんですよ。だから、投影しないと見えないもので、光を当てないとただの壁なんで、ここに映っていた全ての映像は言ってみればフィクションなんですよね。虚空を掴むようなまさに投影された幻影ですよね。だけど、幻影はやはりリアルにひとり歩きをするっていう問題を僕らは少なくとも写 真が、というよりは映画の世紀になった20世紀以来は、そのことと自分たちっていうことの関係は問われるんで、大袈裟な言い方かもしれませんけども、いろいろそういうことを考えさせられるなぁと言う感じなんですよね。
会場Q:改めて、壁を見てるだけなんですよね、いろいろ映ってるんですけども、何か見てる気になってるんですけども。幻影を見てるだけなんだなぁという気がするんですけども。あえてそのお話で申しますと、最後ので、出産シーンを撮る映画の系譜っていうのもある程度ありますけども、先程のお話だと無性に撮りたくなったと、ある意味では人非人の行為なわけですよね、ああいう場面 でカメラに集中できるということは。そういうことを奥さんが言われてらして。だから映画作家っていうのはある意味では人非人にならざるを得ないんだなぁと思いましたけども。あの後、いわゆる家族に関して普段、ああいうビデオでもなんでもいいんですいけども、例えば子供の成長だとか何とかっていうことに関してはそれほど撮影してないんですか?
佐藤A:だから、御法度なんですよ(笑)。だから家の中では一切、ビデオは禁止です。だからビデオ取り出そうものなら「なにすんの」って言われるんで。「あぁー・・」って言ってる間に「すいません」ってなるわけですよ(笑)だから、なにかパブリックなことに家が開かれない限りは無理なんですね。例えば、七五三であるとか、おじいちゃんおばあちゃんが来るだとか、行事であるとか。つまりクリスマスくらいじゃパブリックになんないんですよね、つまり我家の行事じゃないんで。それはそれで致し方ない、人でなしですからこれはしょうがない、罪深き人間は罪に対して無頓着なわけで、例えば裏をかく作戦もあって、連れ合いがいない時に撮影すればいいんだけども、最初子供たちもね、3歳くらいの時は「おとうちゃぁんっ。」って言ってたんだけども、最近はお母さんの影響で撮影拒否になって「お父さん何やってるの!いけないんじゃないのっ。」っていう感じになってね。つまりそこはやはり微妙な距離がありますね。微妙な距離があって、もうダメなのかな・・・と思ってたら最近、突然に家の上の子供が小学校4年で、下の子が1年になって、4年になると性教育が始まるんですよ、学校でね。そうするとね、うちにもすごくいい性教育の教材があるって『我家の出産日記』、さっきやったやつを学校の保健の先生に持っていって、これ見て下さい、とかって言って積極的に外に出るようになって「これは変わったかな」と思って、この前、「じゃあ、うちで見てみようか」って家族で見てみたんですよ。そしたらね、ウケてましたよ(笑)。「お父さん、若い」とかね「お母さん、きれいだった」とかね。やっぱりね、その時の怒りとその時の人でなしと思ったことと完全に切れるんですよね、その体験とは。それでもやっぱり、『我家の出産日記』の中に私がいることは間違いないわけですよ。私にとっていろいろあるけれども、痛いところではなくて、その傷みたいなところがすっと落ちて昇華されて結晶が残るんで、やっぱり人でなしと言われても撮ったほうが、後になるといいという気がしますね。やっぱり映像でも写 真でもなんでもそうでしょうけども、そうした記録性の力が唯一の砦のような気がしますよね。結局、撮るっていう行為は常に暴力であり、カメラっていう機械は常に暴力装置であるっていうことは、どんなにそれをカムフラージュしたって、どんなにそれをいろいろな形で言い訳をしたってそのことは変わんないんですよね。だから撮られた側にとっての痛みはその時はどうやったって解消しない。でも、その痛さとは別 なものが確実にカメラという機械の中に納まるんだっていう問題に、その時間のあるいは歴史の、人間が生きることの残酷さとその無残さとそれからその滅びゆくものと残っていく痕跡っていうのが実にフィクションだなぁっていう問題とさまざまな問題がその中に内包されている。16ミリとか8ミリとか、今日見てもらったこの写 真に関してもそうですけども、全て僕が撮ったやつなんですよね。でも投影した時にはもう僕が撮ったっていう感じは一切ないですもんね。特に今回の映像に関しては、僕が回してるものもすごく多くて、普通 はカメラマンが回すわけですけども、今日見ていただいたほとんどはかなり僕が回してるわけです。だから僕のものかっていうととんでもないですよね。カメラマンが回したからカメラマンのものかっていうととんでもない、というのと同じくらいに僕が回したからって僕のものではないし、こうやって笹岡さんに(写 真を)選んでいただいたんですけども、ほとんど僕がこうやって見ても撮った記憶ないですもんね。なんでこんなの撮ってんだ、バカじゃないかって思うわけですよ、こうやって見るとね。確かに俺ここにいたなぁ、という記憶が半分くらいある程度。それがやっぱり記憶の本質に近いような気はね、して。人でなしでしょうがないじゃないかということなんですけども、人でなしは人でなしなりに、「人でなしの魂にも五分の魂」じゃないけども(笑)。
会場Q:残るものに対する信頼感みたいなものがあるわけじゃないんですか?
佐藤A:家の人達に?
会場Q:いえ、佐藤さんに。
佐藤A:あ、僕にね。そうそう。
会場Q:やっぱり素材にされたっていうのがあるわけですよね。自分が人間としてではなく素材にされたっていう感覚があって。そこには暴力性がありながら残るものへの信頼感みたいなものがあるからこそっていうのもあると思うんですよ。その信頼感っていうのが決定的に揺らいだことっていうのはあります?
佐藤A:あ、僕はね、信頼感はいっつも揺らいでるんですよ。揺らいでるんですけども、どうにかなるだろうなって高を括ってるとこがあるんですよ。もう全然信頼してませんよ。自分で映画撮ってていっつも俺はダメだなっていうふうに思うんですけども、だけども、どうにかなるだろうなっていう無前提の確信だけはあるのね。それはなんかよくわからないんですけども、つまり物事を裏返して言えば、これを撮れたら映画になるっていうふうに思ってないからかもしれないですね。確固たるものがいつも無いんですよね。だから『我家の出産日記』だってこの出産のシーンがあればいいんだっていうことじゃなくて、この膨大になんか日常の時間をとってるわけですよね。そしたらなんか出産シーンが撮れなくてもいいんじゃないかなと思いながらも膨大に何もない時間をとってるわけですよね。だけどもやっぱり出産のシーンも撮りたいと思って、ま、これはこう切り裂かれるわけですけども。でもこれがあればこれは終りだっていうことは僕にとっては一回もなくて、だから並べてみないと実際には何もないかもしれないなっていうふうにしか素材に関しては本当の意味では僕は信頼してないんですよね。
会場Q:撮ってる佐藤さん自身も素材の一部っていう?
佐藤A:いや、僕は素材というよりはやっぱりこの機械の中に入ったものを並び替える作業が僕の仕事っていうか位 置なんで、機械に入ったものをどう並び替えるのかっていうことに関しては、随分考えるけども、機械に入ったものに対して、これでどうにかなるっていう信頼は実はあんまりないんですね。だから他の人が撮った素材でも僕の回路に入ってくれば映画になっちゃうよっていう変な確信はあるんですよね。それで他の人の映画の編集もしますけども、最近はしませんけども、喧嘩になるだけだし、おもしろくないんで、しないんですけども、あ、できるなっ思ってしまう傲慢さはあるんですよ、僕の中でどうしても。それが信頼なのかどうかはわかりませんけどもね。

会場Q:青森のも面 白かったんですけども、ベルトフの『カメラを持った男』を思い出すんですけども。そういうイメージではなかったんですか?
佐藤A:あ、あれは僕は塚本慎也の『鉄男』だったんですけども(笑)。疾走しようっていう。単純で。あれくらい疾走できたらいいなって思ったんだけども。ベルトフほどの問題意識はなかったんだけどもどちらかというと、青森っていうこともあって、足立正生の『略称連続射殺魔』っていうのは意識しましたよね。やっぱり町を疾走することによってその風景の中でいろんなものが出てくる。『略称連続射殺魔』の映画自体がとにかく疾走するでしょ。あれがすごく新鮮で、しかもあれは今見るからおもしろいんですよね、当時見るよりね。70年代のまさに様々な風景が写 っていて、とっても新鮮で、最果ての地なんてものじゃなくて、別のものが映り込んじゃってて、最近僕、また見たら、すごくおもしろいんで、びっくりしましたけども。でも、それはこの映画のモチーフにもありますね。つまり、今ある青森が今の青森のままでずっと継続しませんので。東京が崩れていくように青森も崩れていく。別 に青森だけが崩れていくわけじゃないんだけども、どの地方都市も駅前がどんどんダメになっていくように、駅がどんどん虫食い状態で蚕食されていく。それは青森だけじゃなくって地方都市が没落していくっていう問題なんで、そこのせめぎ合いがこの町の風景の中に見えるわけですね。だから新しい建物っていうのは少しも100年先のことを計算していない。そんな張り子の虎のような巨大ビルを駅前に建てるわけですよね、地方都市のね。それは、東京がその街殺しをやってきたんだから。そういうことが結局、映り込むなとは思ってましたよ。だからわざと町のはずれを、あの、あの辺はすごい恐いヤクザの人たちがいっぱいいるんですよ。ガラガラ台車を押してるとね、「君たち、来るところじゃない」とかなんとか言われてね。だから「キッズアートワールドですっ!」っていうんだけど、「ここは子供の世界じゃないんだ、ここは。帰んなさい。」とかって言われてね、「ま、そう言わずに、ガラガラ・・・」なんてやってましたけどもね。そういういろんな意味で軋んだり、痛んだりしてると思うんですよ、あの町自体がね。それは東京だって同じですよね。それだけを焦点にしてこのアートキッズをやろうとは思っていませんけど、それが10年経つとね、あ、そうだったな、なんて思えると思うんですよね。それは足立正生の『略称連続射殺魔』が優れていたのは永山則夫っていう人の歴史だけではなくって、戦後っていう非常に抽象的ですけども、確固たるもの、それを60年代から70年代の映画の中に映っちゃってる。それはあの映画をずっと普遍なものにするひとつの道だとしたら、単にアートイベントをやりましたっていう記録を作ってもそれは2001年にイベントをやったってことに過ぎないんだけども、やっぱり青森県という町が、どうやってあの時にどういう姿をしてたのかっていう一端でもね、子供をダシにして作品化していけば、それはそれでなんらかのまさに痕跡になるかなっていうのは考えましたね。先程言われたこととちょっと近いですけども、僕なりのここで残しておくことは絶対やるべきだっていう理屈はあります。でもそんなものは、いいんですよ、映画のあとでくっついてくるもんでね、おもしろおかしくワハハッてやってもらえればいいんだけども、そういうことも多少は考えてるかもしれませんね。ま、そんなんで長時間すみません。ありがとうございました。