試評 2004.03.11 by 土屋誠一
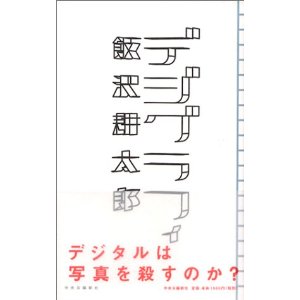
銀塩写真の終わりが囁かれ始めて久しい。デジタルカメラのマーケットシェアは、旧来の光学式カメラのそれを上回り、早晩駆逐し去ることは、もはや止めようもない。単体のデジタルカメラのみならず、CCDはモバイル機器のほとんどに標準装備され、数年前には誰もがそう感じたような珍しさをもって、それを見る者はいなくなった。カメラ付きの携帯電話でさえも、既に単体のそれに劣らぬ画素数を持ち、今やカメラ付きの携帯電話なのか、携帯電話付きのカメラなのかを区別することすら馬鹿馬鹿しいほどである。デジタルカメラが身近になり、誰もが撮影行為をする昨今、写真美学、写真批評の領域においても、その認識の枠組みを再考せざるを得ない地点に逢着している。
飯沢耕太郎が去る1月末に上梓した『デジグラフィ デジタルは写真を殺すのか?』(中央公論新社)は、そのような現況において、待望の書物である。個別的な写真による表現の観点から、デジタル写真、あるいはデジタルイメージに関して述べられた書物は、これ以前には(少なくとも日本においては)存在しなかった。自身の表現を、デジタルカメラに特化して行う作家が、既に少なからず存在している現在、飯沢らしい着眼の素早さは、さすがである。ただ、その内容が時事的であるという宿命上、数年後には古びてしまうであろうこともまた、事実である。そのため、この書物を読む者に求められることは、ここに書かれている事項の全てをすぐさま理解し、そこから派生する新たな思考を生産することである。そしてまた、そのような思考様式こそ、非物質的なデジタル写真の速度に似つかわしいだろう。本稿では、この書物で提出された枠組に概ね沿いながら、逸脱も含めて述べてみようと思う。
始めに、デジタルカメラがもたらした、カルティエ=ブレッソン流「決定的瞬間」の崩壊について考えてみよう。飯沢は大西みつぐの言を引きながら、液晶ディスプレイで「上がり」を確認しながら撮影すること、また気に入らなければ撮影したショットをメモリ上から消去できることを、その理由に挙げている(pp.132-138)が、ここではそれとは少し違った視点にその理由を求めてみたい。
スティルカメラと映画のカメラが、その機能的差異において、その弁別に意味があったのに対して、いわゆるデジタルカメラとデジタルヴィデオの差異は、ほぼ無いと言える。デジタル画像の動画から、静止画を得ることは、そこからより良い一部分をサンプリングすることで、簡単に可能になる。さらに言えば、デジタルカメラの場合、それが静止画用であれ動画用であれ、いずれにせよ常に動画を撮影し続けている。このことは、デジタルカメラに装備されている液晶ディスプレイを見れば容易に理解できる。そのディスプレイは、銀塩カメラのファインダーとは、原理的には全く関係がない。液晶ディスプレイは、CCDが受光=撮影した外界のイメージを、リアルタイムに反映しているイメージである。つまり、デジタルカメラのシャッターボタンは、あくまで銀塩カメラの慣習をシミュレートしたものに過ぎず、むしろそれは動画撮影のカメラの、録画ボタンと全く同等のものであり、その場合のシャッターボタンは単に録画するか否かを決定するためのトリガーに過ぎない。
飯沢は、スポーツの報道写真において、従来ならば、スタートやゴールのような決定的瞬間が起こり易い場面を特定して撮影する、銀塩カメラの撮影様式から、一連の競技の推移を、スタートからゴールまで、ひたすらシャッターを押し続ける、デジタルカメラの撮影様式へと変化したことを例に挙げている(p.69)。このような撮影様式が選択される理由は、銀塩カメラの時代とは違い、記憶媒体の容量が飛躍的に増大している現在のデジタルカメラでは、決定的瞬間の一コマを狙う撮影様式よりも、一連のシークエンス全てを記録したのち、その中から決定的瞬間になり得る部分を抽出したほうが、より合理的であるからだ。
ここから理解できることは、モダニズムの写真がその拠り所にした「決定的瞬間」が、デジタル写真の登場によってなし崩しにされたということだ。モダニズムの還元主義は、写真に限らず瞬間性の相を要請したが[註1]、それはだらだらと続く持続性の相へと転換されてしまった。あるいは、次のように言い換えるべきであろうか。イメージの交換不可能な単独性やその強度を表象する「決定的瞬間」性は、持続性の下に埋没する可能性の淀の中に放り込まれ、限りなく遅延される、と。この瞬間性の遅延は、ソリッドな物理的支持体を基盤にする銀塩写真とは違い、相対的な可能性の束に開かれている。
相対的な可能性には、デジタルイメージの改変性に容易に結びつく。とりわけ報道においては、その真実性が求められるが故に、その改変が厳密に禁止されているという(p.72-80)。しかしながら、この禁止は、デジタルイメージのメディア的特質にとっては何ら本質的なものではない。データ上での改変は、出力されるイメージに何ら痕跡を残さないデジタルイメージの場合、旧来のフォトコラージュのような触覚性(文字通り「手を汚す」といったような感覚)が強く意識される場合とは違い、ほとんど倫理的な感情を作動させることなく、それを完遂させるであろう。ジャン・ボードリヤールはディスプレイのようなインターフェイスを通した画像を、器官的な接触を介さない、直接的な眼の接触として捉えている[註2]。その対象との隔たりの無さは、倫理的な禁止を導く他者の介在を許さない。出力されるイメージが、0か1かの数値の差異に過ぎないと還元され得るならば、そのイメージの価値的差異は限りなく相対化され得るのである。
ところで、この書物では、「デジグラフィ」における特質として、その「改変性」「現認性」「蓄積性」「相互通信性」「消去性」といった要素を挙げている(pp.24-29)。「改変性」に関しては先に述べたが、その他の4つに関して若干補足しておこう。「現認性」は、撮影後、即座にその画像を、液晶モニターを通して確認できるということを指す。「蓄積性」は大量なデータの保存と管理に優れている点を指す。「相互通信性」は、インターネットを前提にして、データとして画像をやり取りできることを指す。最後に「消去性」は、撮影された画像データを、簡単に消し去ることができる点を指している。これらは確かに、銀塩カメラではなし得なかった特質であり、その利便性の限りにおいては、肯定的な価値として捉えうるものである。しかし、デジタル写真のメディア的、あるいは美学的特質を考えるにあたり、ここで挙げられている特質に、若干の異を呈してみたい。それは、「消去性」という特質を巡る是非に関するものであり、この特質を認めるか否かによって、デジタル写真の本質は、大幅に違ったものとして立ち現れるはずであるからだ。
フィルムや印画紙といった物理的な支持体に依拠せざるを得ない銀塩カメラの場合、シャッターを切られたり、あるいは印画紙に焼かれたりする行為は、一回性のものである。つまり、フィルムや印画紙といった物理的制限と、それに付随する行為は相補的であり、かつ不可分であるが故に、両者とも不可逆的な時間性に拘束されている。一方、デジタルカメラの場合、行為の一回性の反映としてのデータは、幾らでも交換可能であり、まさに一度記録されたデータを消去した後に、もう一度やり直すことが可能である。その限りにおいてデジタル写真における消去性は、充分納得のいく特質であると言えよう。しかしながら、ここで挙げられる特質のうち、消去性と全く対立する特質を指し示すことができるであろう。それは蓄積性と相互通信性である。
最早スタンドアローン型ではあり得ない現在のパーソナルコンピューティングにおいて、ネットワークの端末に蓄積されたデータは、望むと望まざるとに関わらず、パブリックスペースに向けて完全に開かれている。この開示は、もはや蓄積されたイメージが、パブリックとプライヴェートに分割されることがありえないという事実を示している。このことは、デジタルイメージがインターネット上にアップロードされているか否かということと、原理的には全く関係がない。デジタルイメージは、それが作成されるや否や、潜在的にではあれ、この開示に直面してしまうという事態を、与件としているのである。つまり、デジタルイメージの所在は、必ずしもその作成者の端末に存在するだけではなく、他のサーバー上に、あるいはインターネットのサーバー上に存在するかもしれず、さらにはネット上での公開を通じて、彼自身予想もつかないような他人の端末に蓄積されている可能性すらあるということである。
デジタル写真の最大の特質は、消去性ではなく、むしろ消去の不可能性、あるいはその撮影されたイメージの偏在性にある。物理的な支持体を基礎とする銀塩写真では、ネガとプリントさえ焼却してしまえば、その痕跡は一切残らない。しかし、デジタル写真においては、先に述べたように、当の本人がそれを消去したと思いこんでいても、彼の及び付かない所に潜在しているかもしれないという、ある種の恐怖感に、常に晒されなければならないのだ。飯沢は「デジグラフィ」が引き起こす「儚さ、脆さ、寄る辺のなさ」(p.29)といったような感情を、その消去性と結びつけているが、その消去性はあくまでヴァーチュアルな可能性の一様態として、概念上、消去されたということであり、なんら確実なものとして把握できる認識を引き起こすものではなく、むしろそれゆえに、先のような感情を喚起するのである。
このようなデジタル写真の特質に関しては、芸術の分野でそれを利用している写真家において、よく表れているように思われる。飯沢も指摘している(pp.143-144)ように、日本では、小林のりおがデジタルカメラに限定した制作を、1997年から開始して以来、彼を中心として、ごく若いデジタル写真家たちが見逃せない数登場してきている[註3]。小林以降の「デジタル・スナップシューター」(飯沢の命名による。p.132)もまた、その発表の場を自身が開設するウェブサイトに置いている。この発表形式が妥当なのは、それ自体ヴァーチュアルなデジタル写真を、リアルな場=サイトであるギャラリーで展示するのがナンセンスであるという認識に由来するであろう。目下のところ、自主的なウェブサイトという形式は、美術(あるいは写真)業界における既成の流通経路や文脈に乗らず/乗り得ず、そのような文脈を欠いているが故にアナーキーな表現形式であり、さしずめデジタルパンクス[註4]の様相を呈している。とはいえ、飯沢氏も指摘するとおり(p.184)、どれもが似通ったイメージに見えてしまうのもまた、事実ではある。しかしながら、それは単にデジタル写真家が未だ成熟していないという事を示しているだけに過ぎず、既に興味深い写真家が登場していることも無視できない。その例として、まずは、飯沢も紹介している(pp.179-188)永沼敦子の試みを、取り上げてみよう。
他のデジタル写真家同様、永沼もまたデジタルカメラ+ウェブ上での作品発表という形式を採用している。永沼の「bug train」では、さながら「盗撮」めいた方法によって、電車の車中の様子がスナップされている。そのウェブサイト上には、膨大な数のショットがアーカイヴ化されているのだが、それらを見ていくと、撮影されたどの被写体も、カメラの存在を意識していないことに気付くだろう。ここで撮影された全ての被写体は、車中でのその弛緩した姿を、ウェブ上に晒し続けることになる[註5]。ここで起こっている事態は、次のようなことである。被写体になる者は、当の本人が意識しないうちに、デジタルカメラという不可視の視線によって記録され続ける。無意識の身振り(欠伸、だらしなく広げられた足、居眠り)までもがウェブサイトというパブリックな場に公開され、無限定に流通される。これは一種の監視の形式である[註6]。
現実の車内における窃視者の視線は、窃視される側にその視線を行使する権力の主体を強く意識させるが、永沼が提出するデジタルカメラの視線の場合、その視点の偏在性故、窃視の透明な「形式」であると言うべきである。ベンサム/フーコーのパノプティコンが、囚人に監視者の視線を特定させない技術であったとすれば、デジタルカメラの視線はその特性をさらに強めるものとして機能する。ここでもまた、デジタル写真の特質が、消去性ではないということが理解できるであろう。むしろ、監視の記録は消去されるのではなく、その監視主体を特定できない状態で、ウェブ上に流通されることによって、偏在化されるのである。
永沼の作品を離れて、さらに想像力を働かせるならば、この監視はより拡張され得る。誰もが所持している携帯電話に装備されているCCDが、そのモバイルによって互いを監視しあい、リアルタイムにネットワーク上にアップロードされるという事態がそれである。このような想像は、SF的空想と笑われるであろうか? しかし、相当数の人間が、CCD付きのモバイルを携帯しているという事態には、この既に可能性が潜在している。この事態は、最早どんな些細な身振りであっても、全ての行為がアーカイヴ化され、公共化されるという監視の進行を告げている。ある光景が現実の場所の隔たりを乗りこえ、瞬時に別の場所に転送されるというヴィリリオのヴィジョン[註7]は、あからさまなまでに現実化していると言って良い。ヴィリリオは現実の光景が明示される透明(transparence)性とその光景が隔たった場においても見ることが可能である超出現(transappearance)性とを重ねつつ、その速度によって実現される瞬間性を強調するが、この瞬間性は、旧来の交換不可能な「決定的瞬間」という価値を補強するものでは全くなく、先に述べたようにだらだらと無限に連続する持続性に接続されるものである[註8]。
最後にもう一つだけ具体例を挙げよう。ヴィリリオが述べるようなイメージの透明性、遍在性については、丸田直美の仕事[註9]を参照すべきかもしれない。丸田は、自身が撮影したスナップとともに、NASAの宇宙映像やウェブ上のライヴ・カメラのイメージをも同時に扱う。画面をクリックする度に、次々に現れるイメージは、車窓からの風景から宇宙空間からの風景までの拡がりを持つが故に、文字通り遍在的な視点を表すのと同時に、地球規模での監視の視線をも表している。その上興味深いことは、単に一アーティストに過ぎない、極めて小さな存在によって、全世界的視点が(潜在的にであれ)獲得されてしまっているという事実である。
ここで紹介した、デジタル写真家たちによるヴィジョンが、社会や政治の局面において一般化される/されているならば、それは決して望ましいことではあり得ないであろう。しかしながら、これらの試みが示していることは、終末論的なヴィジョンの肯定ではなく、現状に正確に反応した身振りであるということに注意すべきである。我々が為すべき事は、永沼や丸田らの試みを正確に認識し肯定した上で、それを抵抗の論理にいかに接続されうるかを模索することに他ならない。デジタル写真が抵抗のための装置足り得るか、あるいは退屈で危険な現状肯定の装置に陥るかは、「デジグラフィ的不安」(p.219)の恐怖を通して、銀塩写真を肯定するという身振りにではなく(p.232)、むしろその不安の根源を明確にし、内在的に批判していくという試みに賭けられているのである。
[後記]あまりにも煩瑣になるため、文中で取り上げた固有名から、すべて敬称を省略させていただいた。
[註2]ジャン・ボードリヤール『透きとおった悪』塚原史訳、紀伊國屋書店、1991、p.77。
[註3]批評家の大嶋浩が自主発行している『Declinaison』という小冊子を通観すると、現在のデジタル写真家のある種の傾向と、その理論的枠組が理解できる。参照をお薦めする。この冊子は2002年から刊行されはじめ、現在では1冊の特別号を除くと、6号まで刊行されているようだ。
[註4]この言い回しに、かつてのウィリアム・ギブスンやブルース・スターリングといった「サイバーパンク」を想起する向きがあるだろう。80年代以降の、いわゆる「メディアアート」の問題設定は、サイバーパンクと明らかにリンクしているが、それらがあまりにもコストがかかっている(ICCを見よ)のに対して、極めてロー・コストな現在の「デジタル・スナップシューター」たちは、”punk”という概念の本来的な意味にとって、よりその称号に適っている。
[註5]ここでは、永沼の「Bug Train」の先駆として、瀬戸正人の仕事を想起しておこう。銀塩写真とデジタル写真との差異に注目していただきたい。瀬戸正人『Silent Mode』(MOLE UNIT NO.5) Mole、1996。
[註6]ルイス・ボルツや伊奈英次の視線が、監視をする装置そのものに向けられているのに対して、デジタルカメラの視線それ自体が、監視の形式を代行してしまうという差異に注意しなければならない。伊奈の場合、デジタルカメラで撮影しているので、さらにややこしくなるが。
[註7]以下を参照。ポール・ヴィリリオ『瞬間の君臨 リアルタイム世界の構造と人間社会の行方』土屋進訳、新評論、2003。
[註8]別の所で、ヴィリリオは映画を論じながらも、このような事態に的確な言葉を与えている。「あらゆる芸術は死、つまり瞬間の惰性に類似し、生の時間秩序に生じた変速現象であることをわたしたちに教えているのだ」。ポール・ヴィリリオ『戦争と映画 知覚の兵站術』石井直志・千葉文夫訳、平凡社ライブラリー、1999、p.101。
[註9]丸田直美に関しては、彼女のHPとともに、先に紹介した『Declinaison』の4号(2002)を参照していただきたい。